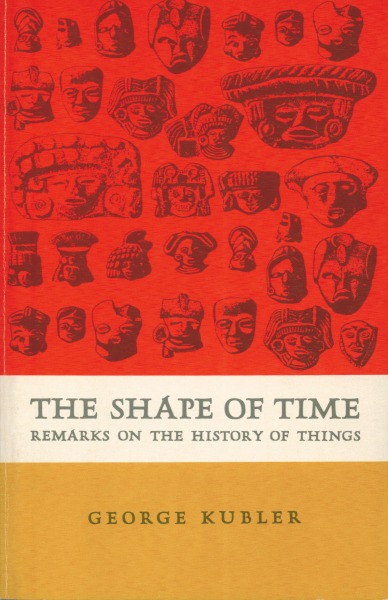スンバワ島はプロペラ飛行機で上空からみた時も荒れ果てた土地ばかりであった。火山をいくつも抱え(アトランティス伝説地の一つでもある)、何回にも渡る溶岩流が島の相当の部分を覆い尽くしている。山の開墾は困難で、多くの村が平地の川沿いに位置していた。日差しは強い。
そのなかでDonggoの集落が異なっているのは、それが山の尾根に位置していること。これらの集落がイスラム化を嫌い奥地に入っていた人々のなした結果であることは先の報告で述べた。海からやってきて平地を浸蝕するイスラム教化(イスラム教のことを悪く言っているのではないので念のため)をさけて、水へのアクセスを犠牲にして、見晴らしのよい高台に集落を築き上げたのだ。この開墾された成果をみてほしい。苦労はいかばかりのものであったかと思う。
 |
| 送信者 20130819 Donggo, 7thC hindu remain, salt fields |
申し訳ないが、スンバワ島にはあまりみるべきものがない、と佐藤氏が言ったのだが、彼らの米倉をみて、その特殊な構造に感じ入ってしまった。精緻な事例を見せられないのが残念だと言われつつ、しかしそのエッセンスはよくわかる。
まずこれはDonggoとは別の村、Wawoにあった米倉の集合体。今でも現役である。ちょうど切妻が浮かんだ形の米倉をLenggeといい、壁つきの米倉をJonpaという。
 |
| 送信者 20130818 Wao, Wao2, Wera Timur |
この集合体を高床下から撮影するとこんな感じである。ちょっと普通にはない光景である。
 |
| 送信者 20130818 Wao, Wao2, Wera Timur |
さて、Donggoではこれが米倉ではなく住居になっているというのであった。
Donggoは彼らの信仰の対象である火山であったDonggo山をみあげる、より低い山の尾根に位置している。その尾根状にできた集落をながめて意味もなく興奮する。やはり困難な場所に成立して、安定状態を保っている集落をみると人間の知恵を感じるからであろう。
さてこの村では先の米倉形式が住居として活躍していた。今でもこの形式で新築されている。いくつか風景を上げる。
 |
| 送信者 20130819 Donggo, 7thC hindu remain, salt fields |
 |
| 送信者 20130819 Donggo, 7thC hindu remain, salt fields |
 |
| 送信者 20130819 Donggo, 7thC hindu remain, salt fields |
 |
| 送信者 20130819 Donggo, 7thC hindu remain, salt fields |
この形式の独創的な点は、ネズミ返しをもつ4本柱とそのうえに位置する家屋空間が完全につながっていないことである。溝で引っかかっているだけである。UFOとそのターミナル(発着台)とでも言えばいいのだろうか。それぞれが自立しているのである。
そのため高床の柱自体に強固な構造が必要になる。この形式の高床下のテラスには独特のかたちをした、一般にいわれるところの、方杖という斜材が用いられている。
 |
| 送信者 20130819 Donggo, 7thC hindu remain, salt fields |
方杖は隅部分があらわれる柱部分できちんと45度にカットされる。いわゆる”留め”の形式である。そして柱に込栓される。方杖のもう一方はテラスを渡す大引を二本渡し、その間に方杖をねじらせながら入れ、栓で止められている。
 |
| 送信者 20130819 Donggo, 7thC hindu remain, salt fields |
上記詳細は、いたずらに手の込んだものではなく、力学的な理由付けがある。そしてネズミ返しのついた柱自体も上で井桁で連結される。これでまず第一層が完成である。
 |
| 送信者 20130819 Donggo, 7thC hindu remain, salt fields |
その上に三角の茅葺きの空間か、壁つきの四角い空間が載っている。違う様式なのだが、極論すれば、二種類の空間は交換可能である。この空間の二重の縁の切り方と空間の交換可能性に、メカニカルな面白さときわめて未来的なものを感じた。
このような方式がなぜ生みだされたのか、わからないという。この形式はスンバワでも東地域だけにみられる独特のものなのだ。Donggoのみならず海岸地域にも東スンバワでは普通にみられるものである。
先ほど未来的なものと書いたが、それについて考えてみる。おそらくそれはこの形式が基本的には移動、取り替え可能だからだと思う。それがスンバワの過酷な環境条件の中で成立していることが面白いのだった。状況にあわせて家が逃げていく感じとでも言えばいいのだろうか。カニのイメージがいまでも頭から離れない。